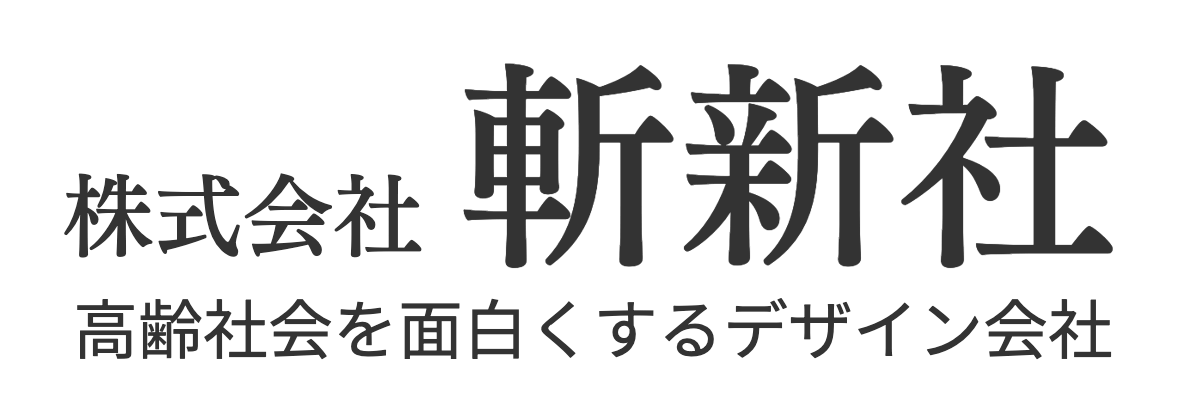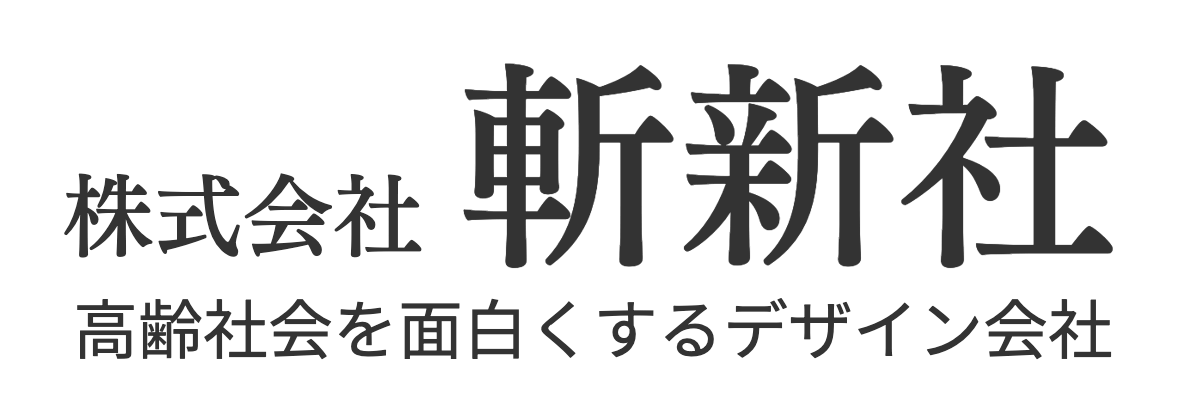【研修】多職種連携・協働に根ざす思考を学ぶ
真のケアチームの一員になろう
2017.11.17-27. 株式会社トーカイさま
2017年11月17日〜27日の間に四回、株式会社トーカイ様の企業内研修で「多職種連携・協働に根ざす思考を学ぶ 〜真のケアチームの一員になろう〜」のテーマで研修をさせて頂きました。
多職種連携の重要性が増す中、連携とはゴールではなくプロセスであり、自分の強み・弱みを理解しておくことが前提であることをお伝えしました。また、自らの既成概念に縛られていては、視界0mの激動の時代に対応することができない。「面白がる」視点と実践で閉塞感を打開する手法をお伝えいたしました。
全国のトーカイの社員様を対象に、全日程で延べ800名近くのみなさまとこれからのトーカイや仕事のあり方を考えました。

自分の仕事を再定義する
連携の前に、「自分たちは何者であるか」を再定義する必要があります。多職種連携のチームでは、それぞれの強みを生かし、弱みはフォローしてもらうことが前提にあるためです。
何者であるか=どんな提供価値(ベネフィット)をもつか、顧客から何が求められているのかを整理することから始まります。そして「自分たちはどのように見られているか」と「本当はどのように見られたいか」のギャップをあぶり出し、理想と現実の差をどのように埋めていくかを考えます。
トーカイ様では、「福祉用具を届ける宅急便ではなく、暮らしをつくる専門職になりたい」との意見が多く聞かれました。

連携とは、ゴールではなくプロセスにすぎない
多職種連携の重要性が注目される中、「連携すること」が最終目的かのように言われることがあります。顔の見える関係をつくることは重要ですが、ゴールではない。多職種連携のゴールは、顧客である利用者さんの暮らしをつくることであり、そのプロセスに連携があります。
その前提を踏まえた上で、どのような利害関係者(ステークホルダー)がいて、それぞれの職種の特性を分析します。現場でどのようなボールを投げ、どのようにパスをもらうか、連携から連動した動きへと関係性を昇華していくコツなどお伝えしました。
弊社で実践している様々なプロジェクトのご紹介により、多職種連携から多業界連携へと視野を広げることで、今いる現場で何ができるかをみなさんと考えました。

ご感想(一部)
・強み・弱みを考えるきっかけになり、それを営業所内の人がどう見ているか、周りの評価を聞けただけでも参考になった。そしてそれは社外でも同じで、自分たちの強み弱み、他職種の強み、弱みを考えたうえで営業活動に活かしていきたい。
・あらゆる見方、視線で「連携」というものを考えさせられました。お話の仕方が上手で、集中して聞くことができ、またお話の内容は勿論の事、トーク術を向上させるヒントを得られたように思います。
・やりたいことを続けるコツが特に印象に残りました。「できるだけ楽しむ・疲れたら現状維持、元気になったら、できることをする。」という私にも実践できることからすることが大切だと感じました。
・発想を自由に持ち視野を広げ、自分の弱みや強みを理解して、周りと協力をして自分の得意を活かし、同じ目標を達成する事が必要だと感じました。
・自分を客観的に振り返る良い機会となりました。改めて自分の強み弱みを向き合い自己研鑚に努めようと思いました。
・自分が未来でどうなっていたいと感じるのと同じように、普段関わっている利用者さんにも同じようになりたい未来があって、それを実現するために多職種のいろいろな人たちとうまく関わって福祉用具事業者としての役割をしっかりと果たせるようにしたいと思いました。
・今まで思った事、考えた事のない発想が多々見受けられ非常に参考になった。今後の業務に活かしたいと強く思えた。
・専門分野外での取組、多方面から捉えた取組により地域や利用者との関係性作りが非常に参考になった。各職種が敷居を低くして協力し合う体制が利用者以外の専門職にとっても知識や経験の向上に繋がると感じた。